遺産承継・財産管理手続業務
身内の方が亡くなった時、その遺産を承継する手続きが必要となります。
相続人の調査確定、遺産の調査確定、それに基づく相続人の全員による遺産分割協議を経て、不動産、預貯金、有価証券等の具体的な承継が決まり、相続登記、預貯金の解約、分配等の手続きをすることになります。
税理士に依頼し相続税の申告をする必要な場合もあります。場合によれば、家庭裁判所に対し相続放棄の手続をすることも必要な場合があります。
私どもは、長い経験に裏打ちされた中から、お客様からご依頼を頂く中で、全体の支援を通じて、紛争を回避し納得と満足がいく解決を目指します。
また、依頼により、遺言書を作成することが必須な場合や作成したほうが良いと思われる場合、相続が開始した場合を想定し、遺言書の作成に関する支援を行うと同時に、相続が開始した場合に遺言執行者として遺言の内容を実現するためのお手伝いを行います。

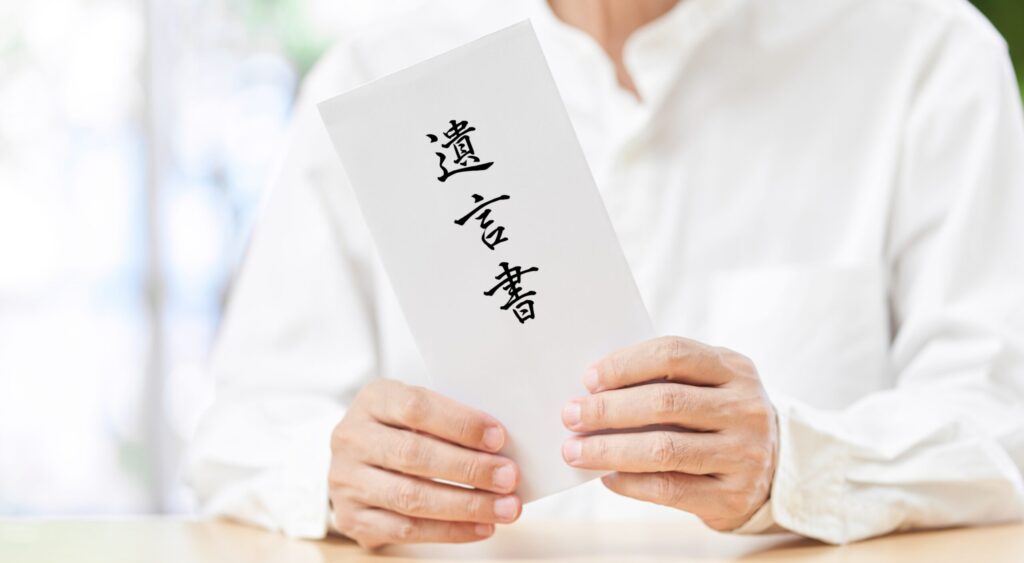

成年後見業務
例えば、相続が開始した場合で相続人の中に精神上の障害により判断能力がなかったり乏しかったりする場合、本人の保護のため、成年後見人等を選任してもらう必要がある場合があります。そのための相談から始まり、家庭裁判所への申立て書類の作成、事案によって家裁の選任審判に基づき成年後見人等への就任することを業としております。
全国の司法書士が、司法書士後見人の育成と監督を目的とした、リーガルサポート会員として25年以上の経験を有しており、これまでに累計200名近い人への支援を行っています。
不動産登記、商業・法人登記手続業務
司法書士といえば登記というように、登記は司法書士の本業とも言えます。
土地や建物(不動産)を売買等により取得した場合には、権利を確実なものにするため、登記(対抗要件)をする必要があります。登記は早い物勝ちですので、常に迅速、正確かつ丁寧にを心掛け手続きを行っております。
令和6年4月1日から法改正によって、相続等により不動産を取得した相続人及びそれ以前に開始した相続であっても、未登記のものも3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料の対象となることがあります。
当事務所では創業以来40年にわたり、相当数の難しい相続登記を積極的に受託処理した実績を有しております。明治・大正・昭和初期に設定された古い抵当権等の担保(休眠担保といいます)の抹消手続きや、会社法人の設立は当然のこと、合併等の組織再編に関する登記手続きに実績を有しており、安心してご依頼いただけます。



簡易裁判所の手続代理業務
債務整理、所有権を移転するための判決の取得等簡易裁判所の手続(訴額が140万円以内)においては依頼者の代理人として手続きを行っています。
裁判所提出書類作成業務
近時、積極財産が消極財産を下回る(負債が多いこと)場合等以外にも不動産に対する認識の変化により、家庭裁判所に相続放棄の申請をすることが増えてきました。
他にも破産手続開始・免責許可決定申立、成年後見等開始申立、自筆証書遺言書の検認申立、遺言執行者の選任申立、不在者の財産管理人選任申立、相続財産清算人選任申立等の書類作成を日常的に行っています。

お問い合わせ
ご相談は無料
まずはお気軽にご相談ください。
